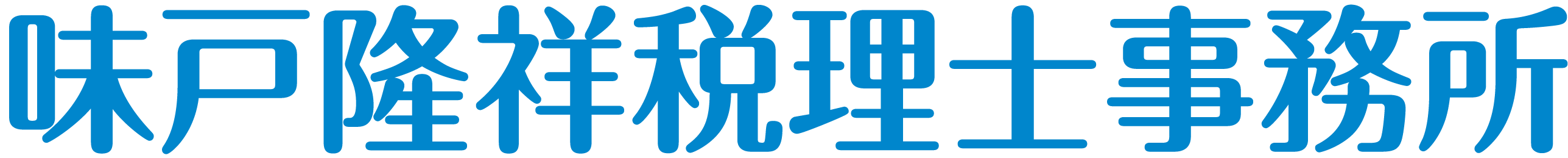【時事解説】高まるSDGsへの関心と企業の取り組み その1
SDGs(エス・ディー・ジーズ)という言葉を耳にする機会が増えました。SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2016年から2030年の15年間で達成する世界共通の目標(ゴール)を指します。内容は、持続可能でよりよい社会の実現を目指すものとなっています。目標は全部で17個あり、社会が抱える数ある課題を凝縮したものともいえます。
具体的には、1貧困をなくそう、2飢餓をゼロに、3すべての人に健康と福祉を、といった途上国への支援に関するものから、ジェンダーの平等や働きがい、経済成長、気候変動への対策まで含まれます。人・社会・地球などの望ましい未来像を実現するための具体的なルールを集大成としたものでもあります。
もともと、大企業を中心に、CSR「Corporate Social Responsibility(企業の社会的責任)」が浸透している会社は多くあります。こうした企業は倫理的観点から事業を展開して、社会に貢献しようと考えます。すでに浸透しているCSRとSDGs、両者の違いはどこにあるかというと、CSRは経済・社会・環境のバランスを重視するといった概念的なものが中心になりますが、SDGsは具体的な目標が定められており、より取り組みに直結しているといえます。
すでに、政府はSDGs推進本部を立ち上げており、94もの自治体がSDGs未来都市に選定されています。企業では、大手の自動車をはじめとする製造業のほか、流通や建設、金融など、さまざまな分野で取り組みが始まっています。TBSではSDGsプロジェクトを掲げ、2021年4月26日~5月5日をSDGsウィークとして番組を構成しました。今後、さらに多くの企業での取り組みが始まることが予想されます。(つづく)
(記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)