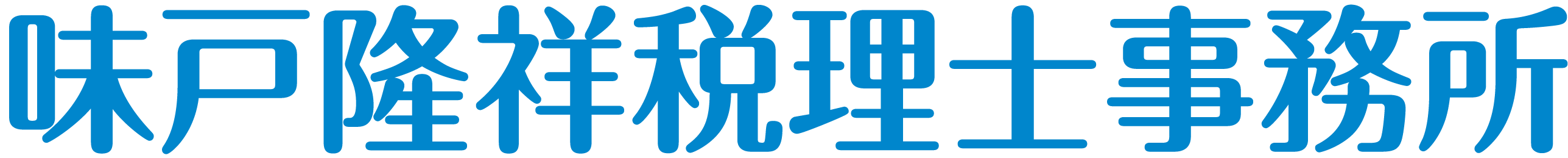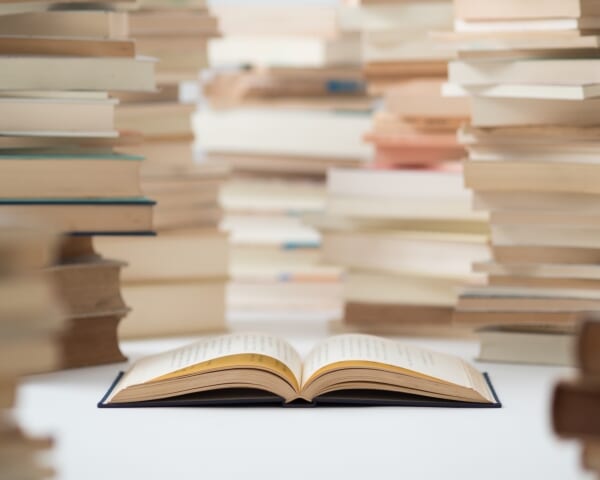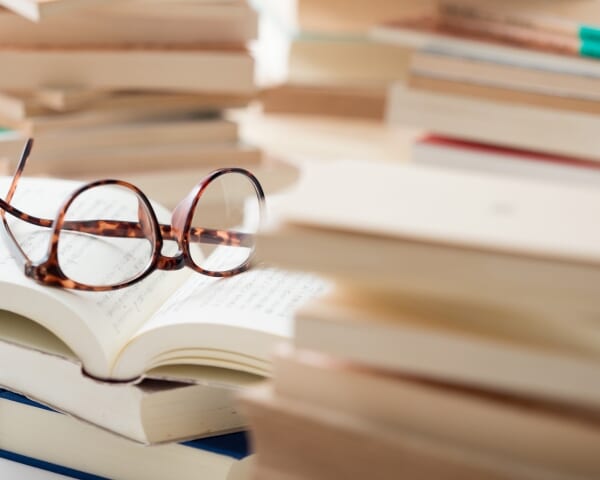
《コラム》給与から徴収される税金
◆2年目から手取りが減る? 新卒で入社した方は、この春が初任給という方も多いでしょう。日経新聞がまとめた2026年度採用計画調査によると、物価上昇を背景にしてか25年度の初任給を30万円以上とする企業が24年度から倍以上に増えたそうです。 給与から徴収される税金は「所得税」と「住民税」ですが、住民税については昨年1~12月の所得や控除で今年6月からの住民税が計算されるため、新入社員の1年目の給与からは学生時代のアルバイト量がよほど多くない限り、住民税が徴収されません。2年目6月の給与から、1年目の所得や控除に応じて住民税が天引きされるようになるため、手取りが減るという現象が発生します。初任給から2年目の給与が10%以上増えれば話は別ですが、昇給率がそこまで高い会社は珍しいでしょう。 なお、転職の場合は前の会社で異動届出書を作成、新しい会社に提出していれば住民税の特別徴収が継続されます。 ◆所得税の源泉徴収義務 給与所得に対しては所得税・住民税共に「事業主が徴収しなければならない」とされていますが、除外される例外もあります。所得税の徴収義務の例外としては、扶養控除等申告書を提出している場合、給与収入が月額88,000円未満であれば徴収しなくてよいことになっています。 ◆住民税の徴収義務 住民税の天引きについては「特別徴収」と少し呼び名が変わります。また、徴収義務は所得税同様ありますが、以下の場合は天引きではなく納税者が納める「普通徴収」でもよいということになっています。・事業所の総従業員数が2人以下・別の事業所で特別徴収・給与が少なく税額が引けない・給与支払いが不定期(毎月でない)・事業専従者(個人事業主のみ対象)・退職者又は退職予定者(5月末まで) ◆ご利用は計画的に? 一般的な会社勤めであれば、所得税と住民税は天引きされるのが普通ですが、2年目新たに発生する住民税の徴収は所得税と比べると税率が10%固定の分、稼ぎがまだ少ない新人にはそれなりにつらい手取りの減少となります。職場の先輩方は2年目から住民税が徴収される旨を早めにアドバイスしてあげるとよいかもしれません。