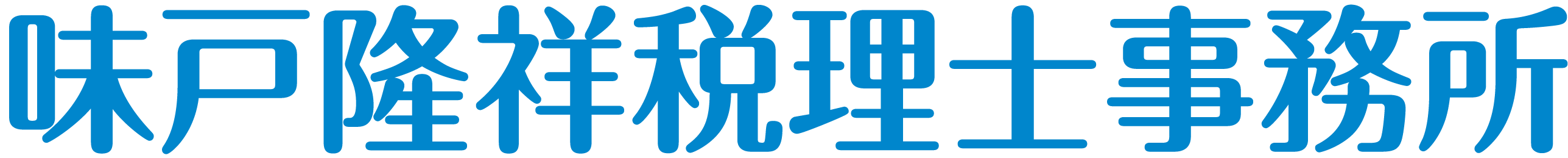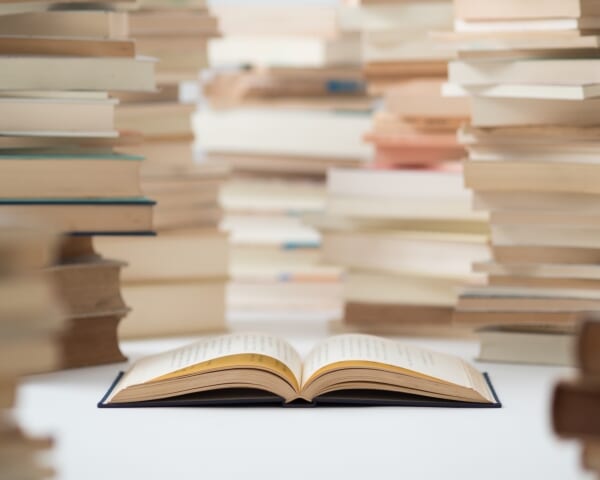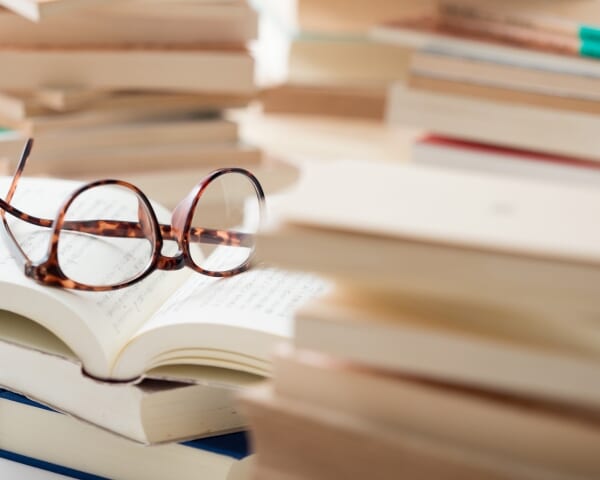【時事解説】スマートシティーで生活はどのように変わるか その2
スマートシティーの実証実験が進んでいます。スマートシティーとは、ITや環境技術などの先端技術を駆使した街づくりを指します。国内でスマートシティー関連事業に取り組む地域は現在160ほどあります。 福島県会津若松市を例に挙げると、同市では様々な実証実験が進められています。観光名所の鶴ヶ城では、新型コロナウイルス感染症対策のため密集回避システムが稼働しています。これは、AIを搭載した3Dカメラが人の動きを感知。人との間隔が1.5メートル以内になると赤色で表示されます。結果、人との距離を保ち、密を避けることができます。 こうしたビジネスチャンスは国内にとどまらず、輸出での利益にも期待が寄せられています。背景には、政府がインフラ輸出に関する新たな戦略を明らかにしたことがあります。従来、インフラの輸出といえば、道路や鉄道といった「重厚長大」が中心でした。が、今後は、ESG(環境・社会・企業統治)分野に重点が置かれるようになります。スマートシティーは環境技術を駆使するため、輸出の強化が掲げられています。 現在、ベトナムの首都ハノイやミャンマーの都市マンダレー、インドなど、東南アジアでは多くの都市がスマートシティー建設を決定しています。1都市のインフラ開発事業に参加するだけでも数百億円規模のビジネスになるともいわれています。これらビジネスチャンスを得るため、政府は日本企業が東南アジア諸国連合(ASEAN)で手がけるスマートシティー事業を後押しする姿勢でいます。 競合する中国や韓国にどこまで対抗できるか。スマートシティー事業が日本に大きな利益をもたらすことに期待したいところです。(了) (記事提供者:(株)日本ビジネスプラン)