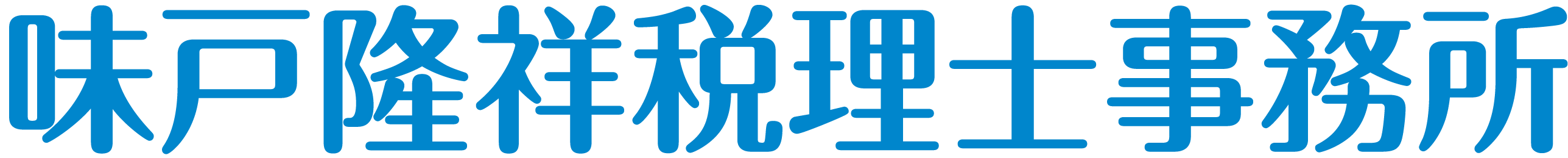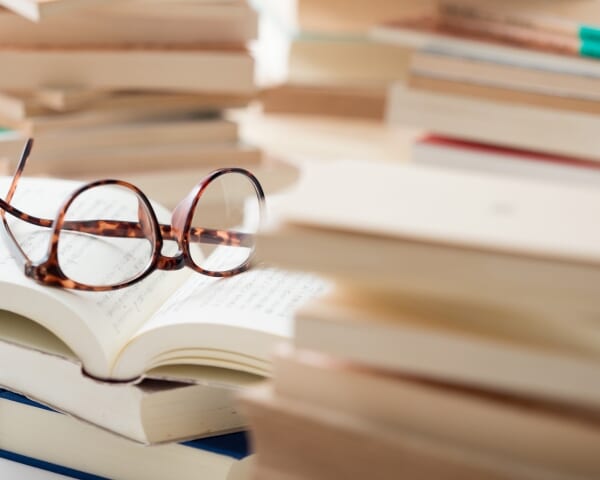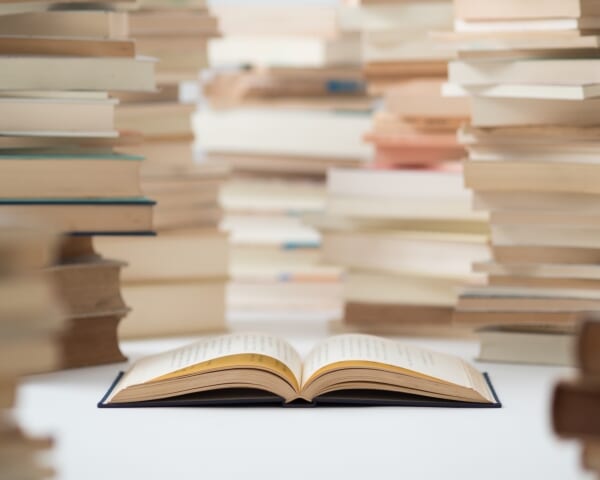
《コラム》法定相続情報証明制度
◆法定相続情報証明制度とは 相続人が法務局に対して、戸籍謄本等の必要書類及び相続関係を記載した一覧図を提出することにより、登記官がその内容を確認し、認証文付の一覧図の写しを交付する制度です。 平成29年5月29日から全国の法務局でスタートした比較的新しい制度です。 ◆なぜ、この制度が必要となったのか? 相続登記や預貯金の解約などの相続手続において必要となる書類は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本等の多くの戸籍関係書類が必要となります。これらを手続ごとに提出し、何度も同じ書類を集めなければなりませんでした。 この法定相続情報証明制度がスタートしたことにより、登記官が内容を確認して交付された認証文付きの一覧図の写しを提出することにより法定相続人が一目瞭然となるため、相続人及び提出先の担当部署の負担が相当軽減されることとなりました。 ◆必要書類 夫、妻、長男、長女という家族で夫が死亡した場合の必要書類を記載していきます。① 夫の出生から死亡までの戸籍謄本② 妻、長男、長女の戸籍謄本③ 夫の住民票の除票又は戸籍の附票 ①~③の書類を収集し、申出書を作成し管轄法務局に提出します。 法定相続情報一覧図に妻、長男、長女の住所を記載して欲しい場合には、上記①~③に加えて妻、長男、長女の住民票を提出します。 ◆最後に 相続手続における戸籍関係書類の収集を1回にし、法務局に提出することにより戸籍関係書類に代わる法定相続情報一覧図を交付してもらい、相続人の戸籍収集の負担を軽減し、提出先(銀行等の金融機関)の担当部署の戸籍謄本等の解読が不要となり法定相続情報一覧図によって明らかになるということです。 相続人にもメリットですし、提出先にもメリットともなるので積極的に利用していきたい制度です。