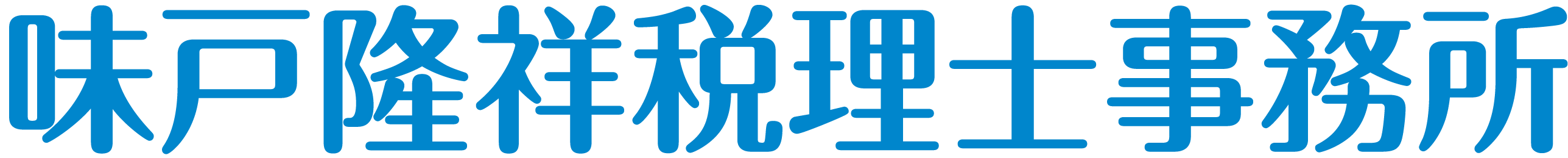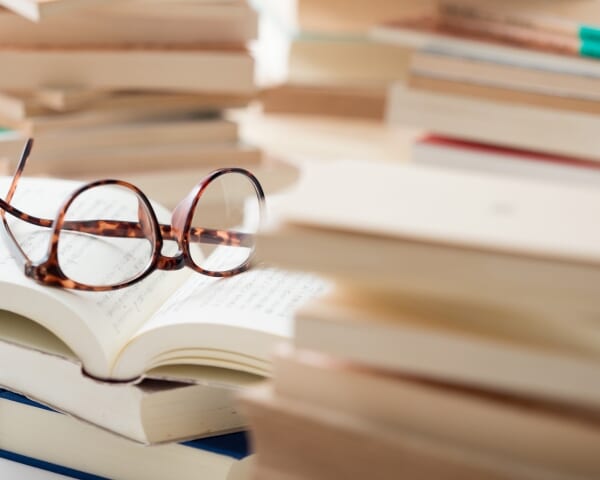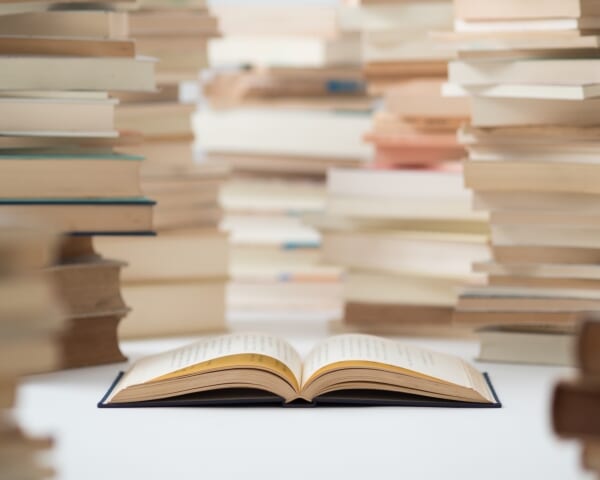
《コラム》印紙税の豆知識
◆売上の領収書でも印紙税がかかりません 営業目的の売上の5万円以上の「領収書」には、その記載された金額により印紙税がかかります。それは印紙税法の第 17 号文書「金銭又は有価証券(小切手・手形等)の受取書」に該当するためです。 しかし、17号文書の「課税物件」欄の文言をよく読むと、「金銭又は有価証券の受取書」となっております。今はやりの電子決済やクレジットカード取引等の信用取引では現実に金銭や有価証券の授受を伴いませんから、売上にかかる「領収書」でも印紙税はかかりません。ただし領収書に「○○電子決済」や「クレジットカード決済」等と明記しておく必要があります。 電子決済といっても事前に入金しているような前払支払方式や即時決済等、信用取引ではない場合は金銭の授受と見なされ、「領収書」は17号文書となり印紙税がかかります。 ◆5万円に消費税は含まれるの? 5万円以上の領収書には、記載された金額により印紙税がかかることは周知の通りです。最高で20万円(10億円を超える金額)の印紙税がかかりますが、消費税が含まれるのかどうかで10%の差が出ます。 例えば46,000 円の商品を販売すると消費税が4,600円かかります。お客様から50,600 円を頂戴して「領収書」を発行するときに、単に合計で品代50,600 円とだけの記載ですと印紙税はかかります。しかし「消費税の金額が区分記載されている場合は、消費税の金額は、記載された受取金額に含めない」という税法の規定がありますので、次の①又は②のように記載すれば印紙税はかかりません。①商品代金46,000円 消費税及び地方消費税4,600円 合計50,600円②商品代金50,600円 うち消費税及び地方消費税4,600円