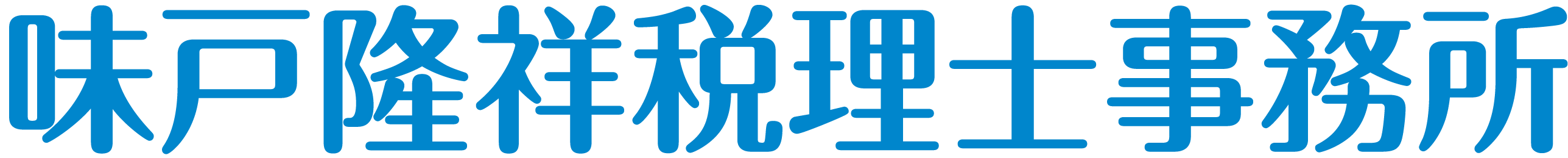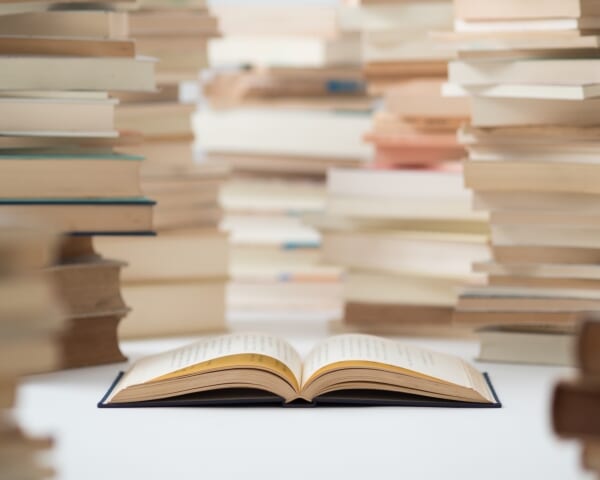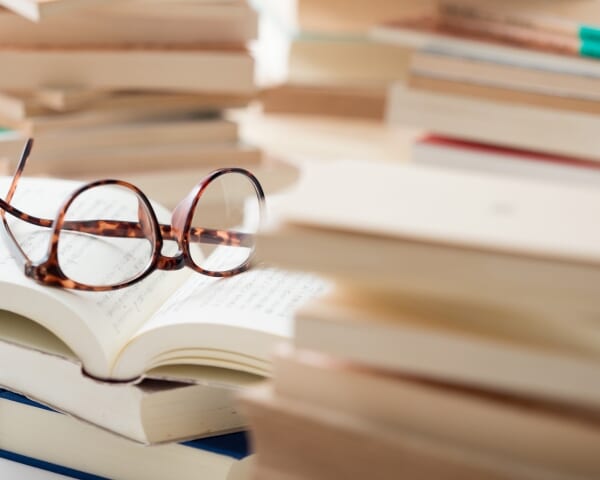《コラム》電子申告では余裕をもって不測の事態に備えましょう
◆申告・納付の期限日にトラブル発生! 仕事始めの令和4年1月4日、国が運用しているe-Tax(国税電子申告・納税システム)において、受付システムで処理が遅延するトラブルが発生しました。 正午過ぎに申告書の提出手続きをしていたある企業では、電子申告後、即時通知では正常送付が確認できたものの、その次の段階で通常届く受信メッセージが届かず、電子納付の手続き前で先に進めなくなってしまいました。数日前に行ったe-Taxソフトの最新バージョンへの更新が原因なのか、それとも自社のパソコンや通信環境が原因なのかわからず、少し狼狽したようです。 e-Taxのホームページサイトで確認したところ、緊急のお知らせが発信されていて、原因はe-Taxにあることがわかりました。9時ごろから発生していたこのトラブルのお知らせの第一報は午前11時には出ていたようですが、13時になっても、16時になってもトラブルは解消されず、ようやく20時になって復旧したようです。 ◆期限後申告や期限後納付となるのか? 復旧した20時まで待ってその後の作業を行っていれば当日中に手続きが終わったでしょう。しかしながら、復旧を知らずに手続きが期限日の翌日(令和4年1月5日)となった場合には、期限後申告や申請、期限後納付となるのでしょうか。2年連続の期限後申告で青色申告取消とか、消費税の届出書の申請が間に合わず最悪の事態に面しそうなケースもあるかもしれません。 e-Taxでは、「期限後の申告又は申請となる場合、管轄の税務署までご相談ください。」と呼び掛けています。おそらく、「自己の責任によらない、やむを得ない事情として、税務署長に認められる形」で決着するものと考えられますが、実際に期限内での受付が認められるまで不安は残ります。 ◆余裕を持った期限前の手続きが望ましい 今回は原因が国のシステムであるe-Tax側にありましたが、もし、自社のパソコン環境のトラブル(何らかのウィルス感染など)が原因であれば、自己の責任で、宥恕されることなく、期限後の申告・納税・申請になってしまうものと考えられます。 電子手続きを行っている場合には、不測の事態に備えて、日数に余裕をもった手続き体制を整えておくことが望ましいです。